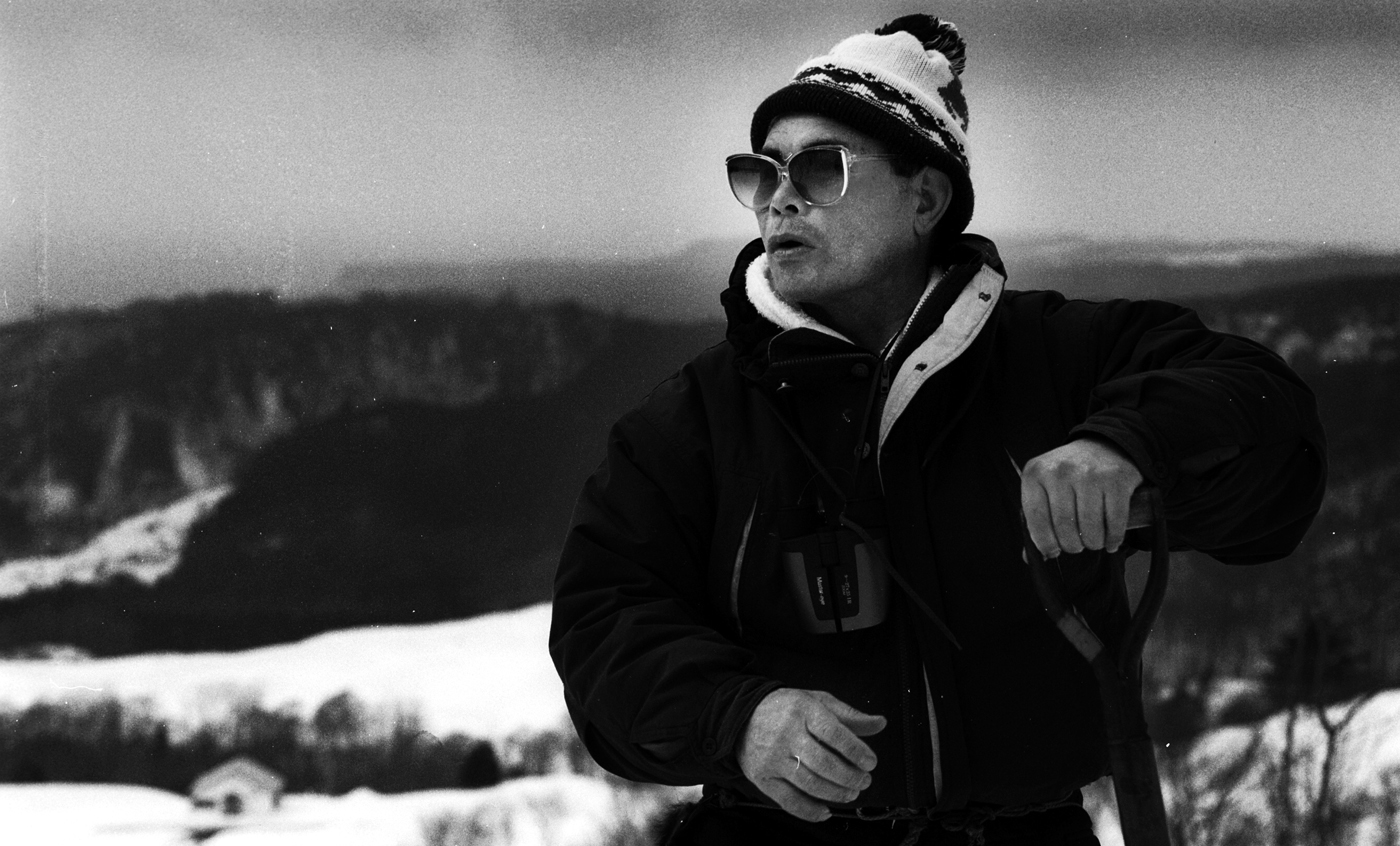家をあけていると気がかりなことの一つに庭があります。ガーデニングと呼べる程のものではありませんが、季節の花が咲く暮らしに憧れて、庭のあちこちに自分たちの好きな草花を植えています。今年は特に雪が多かったと聞き、どうなっているか心配でした=写真上、純白の花をつけたスノードロップ。ヒガンバナ科で、我が家の庭に春一番に咲く花です。寒さに非常に強いとされているだけに、厳しい冬を乗り越えて、今年も可憐な姿を見せてくれました。

そしてこの春、私にはどうしてもやらなくてはならない「宿題」が残っていました。それは球根を植えることです。昨年の晩秋、見切り品として安価に手に入れた球根たち。雪が積もる前に植えようと思っていたのですが、忙しかったのと天候不順にかまけて、放置していました=写真上、購入したものの、ひと冬越えてしまった球根。

封を開けると、中の球根はもう待ったなし。生まれる~!と言わんばかりです=写真上、芽が出てしまった球根。ごめんね、でも植える場所は、ちゃんと確保して、整備しているからね。さあ、作業開始、と予定した花壇へ行ってみると‥。

あれぇー、ものすごく沢山、何者かの芽が出ているんですけれど‥。えーと、どちら様。オロオロと戸惑っていると、通りかかった近所のおばあさんが、「この芽っこ、雪が解けたらすぐに出ていたよ」と教えてくれました。確か昨年も、この辺りにチューリップを植えていました。ズボラして球根を掘り上げなかったために、残っていたチューリップが芽吹いたのでしょう。こんないい加減なガーデナーであっても、花は律儀に応えてくれたようです=写真上、予期せぬ場所から顔を出したチューリップの芽。待機していた球根のために、夫に命じて、急遽、新規の花壇を開拓させました。

その他、庭で見つけた小さい春を紹介します。

以前から片隅にあったフクジュソウも、固いつぼみをほころばせ始めました=写真上、庭の片隅にあったフクジュソウ。今年も可憐な花を咲かせてくれた。

昨秋、植えつけたネコヤナギ。ピンクのぽやぽやした毛が愛らしい=写真上、夫が好きなネコヤナギ。なぜか天才バカボンの主題歌を口ずさみながら手入れをする。バカ‥。ちゃんと根を張り、冬を越したんですね。良かった。


そして、ワサビです=写真上、石垣の下に葉を茂らす天然ワサビ。フキノトウも出るがこっちは雑草として処分。もっと良いフキが山で採れるからね。白神の山には大量に自生していて、石垣下などの日陰に根っこを埋めておくと、翌年の春、思い出したように新芽と葉を出しています。深浦町の魚介の刺身に、若い葉や茎を刻んでツマにしたり、根をすりおろして利用したり。同町の誇る、海の幸、山の幸の最高に美味なコラボレーションです。今年も、いくつかの株が根を下ろして増えたようです。


高知、福岡、東京と、連日のように桜満開の便りが続いています。が、こちらの八重桜はまだまだ=写真上、桜の新芽。まだまだ硬し。満開はいつも、ゴールデンウィーク頃になります。庭でのお花見、待ち遠しいです。

バラの新芽=写真上、面白い形のバラの新芽。春の造形美。アンクルウォルターという品種で、大輪の真紅の花をつけます。昨春、20センチメートルぐらいの苗を植えたところ、一年で3メートルを超える大木になり、ご近所さんをびっくりさせました。今年も期待しています。

暖かい日があるかと思えば、雪花が散る日もあり、北国の気候はなかなか安定してくれません。でも、非常にゆっくりとですが、確実に春は近づいています=写真上、自生するスイセンが力強く芽を出した。綺麗だが、除去するとなると生命力が半端ではなく、かなり厄介者だ、写真はすべて浜田家の庭で。こちらに住んで初めて、春を待ちわびる人々の気持ちが判った気がします。さあ、いよいよ庭仕事、畑仕事のシーズンに突入です。咲き乱れる花を眺めながら、庭でお茶を飲める日が来るのを夢に見て、頑張ります。
Post Views: 461